今回は、男性が育休を取るにあたって、どれくらいの期間取るのがいいのか?
どういうタイミングで取るのがいいか?について。
法律上、子どもが1歳になるまでは、男性もいつでも育休は取得できます。
ただ、育休は取る期間やタイミング次第で、税制メリットが変わってきます。
このあたりを、僕の実体験をふまえて書いてみたので、参考にしてもらえると嬉しいです。
※個々人の家庭や職場環境によって条件は変わってくるので、あくまで僕はこうしたよという前提です。
僕が1月〜3月に育休をとった理由
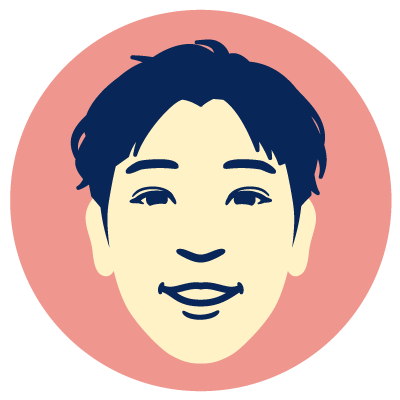
僕は3ヶ月間の育休を取りました。
『なんでその期間にしたの?』についてお答えします。
出産直後が、妻の負担が大きそうだった

まず最も大きな理由として、産後直後の1〜2ヶ月以内が、“産後うつ”になる可能性が高いこと。
発症率は、病院で受診していない潜在的な産後うつも含めると、なんと全体の10〜15%の人が発症するらしい。
結構な確率だよね・・・
産後うつがひどくなると、最悪、死を選択する女性の方もいるよう。
「産後1年未満の女性の死因1位が自殺」というデータまであったりする。(マジか・・)
正直、自分の奥さんは大丈夫かなと思ってた。
でも、実際に僕も育児をやってみて思うのは、ワンオペ育児だったら、産後うつになっても全然おかしくない。
●3時間おきに授乳しないといけない
ミルクは旦那さんも授乳できるけど、母乳の場合は、毎回奥さんが起きないといけない。
●慢性的な睡眠不足になる
授乳した後は、げっぷを吐かせたり、寝かしつけしたり、オムツ替えをしたり。
そんなこんなしてると1時間くらい経って、ちょっと寝たらまた授乳という繰り返し。
●出産後1ヶ月くらいは外出できない
新生児は免疫力が弱いから、1ヶ月くらい外出ができません。
女性は、出産時の身体のダメージも残ってるから、お出掛けもあまりできないようです。
赤ちゃんと家で籠もりきりだと、精神的にキツイかも・・
●はじめての育児は分からないことだらけ
「さっきミルク飲ませたのに、なんで泣いてるの?」「なんで寝ないの?」など、分からないことだらけ。はじめての育児の場合、その1つ1つに不安を感じたりします。
●赤ちゃんの泣き声は想像以上にキツイ
赤ちゃんって、本当にかわいんだけど、ずーーっと泣かれると、辛くなったりします。
泣いてるのは自分のせいなんじゃないかなとか考えちゃいますw
「産前産後の恨みは一生」とも言われるけど、男性の育児に対する向き合い方、奥さんに掛ける言葉ひとつで、信頼関係を壊しかねない。
Twitterに流れる世間の声・・・
奥さんからは、育休取ってくれて助かってると言ってくれてるので、本当に育休取ってよかったなって思います。
仕事上の区切りがよかった

最大1年、育休が取れるからといって、仕事面の不安もありますよね…
僕の会社の場合、4〜9月が上期、10月〜3月が下期と設定されています。
Web制作会社という仕事上、制作物の納期があり、おおよそ3月末までに納品となるケースが多いです。
だから、区切りのいい3月まで育休を取得させてもらって、上期の頭である4月から再スタートしようと思いました。
ちなみに3月くらいに復帰して、上期からの仕事の種まきをすることも考えました。
ただ、奥さんの負担を考えると、3ヶ月くらい育休を取った方がよさそうだったし、僕も区切りのいいところで取った方が、「再スタートだ!」という気分で臨めるかなと思いました。
経済的なことも考えて

育休制度を使うと、6ヶ月間は給与の67%の給付金がもらえます。
社会保険料は免除されるので、手取りだと実質80%以上の補償ですね。
(7ヶ月目以降になると、給与の50%に減額されます)
| 期間 | 育休前と育休中の収入比較 |
|---|---|
| 育休前 | 月額給与 ー社会保険料(健康保険+厚生年金+雇用保険) ー所得税 ー住民税(市民税) ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー =手取り額 |
| 育休中 | 育児給付金(月額給与の67% or 50%) ー社会保険料(雇用保険) ー住民税(市民税) ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー =手取り額 |
詳しくは、こちらの記事にも書いています。
給付金があるとは言え、ボーナスはないし、子どものための貯金も考えると、まず給付額が下がる7ヶ月以上は、現実的でないと思いました。
次に、給付額が最大限もらえる6ヶ月の育休にしようとも考えました。
ただ、そうすると仕事に復帰するのが6月。
上期が9月までだから、復帰するには中途半端だし、上期のボーナスもあまり期待できない。
●仕事に復帰しやすいタイミングがいい
●育児にもしっかり携われる期間は欲しい
●やっぱりお金も欲しい
僕の場合は、この3点を考えて、1〜3月の3ヶ月がベストでした。
家族との時間や、育児と向き合う時間も大事だけど、やっぱりお金も必要です。
育休の税制メリットを最大限活かすポイント
育休開始日は、月末がおすすめ
僕の場合、育休期間は厳密に言うと12/28〜3/31で取得しました。
もちろん出産予定日ベースではあるのですが、育休取得時の社会保険料免除の条件も加味しています。
具体的に免除される社会保険料は、「健康保険」「厚生年金」です。
※免除されるからといって、将来受け取れる年金が減額になったり、健康保険が使えなくなるということはない。
※所得税は所得がないので非課税。住民税も非課税ですが、去年の実績から引かれるので税制メリットがあるのは来年からになります。
ポイントなのは、社会保険料が免除される期間。
育児休業等を開始した日の属する月から、その育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間
令和2年10月28日 第132回社会保障審議会医療保険部会 引用
「育児休業等を開始した日の属する月」ということは、育休を月初に取っても、月末に取ってもその月の社会保険料は免除されるということ。
つまり月末に近ければ近い日程ほど、通常の給料ももらえるし、社会保険料も免除になるのでお得ってことですね。
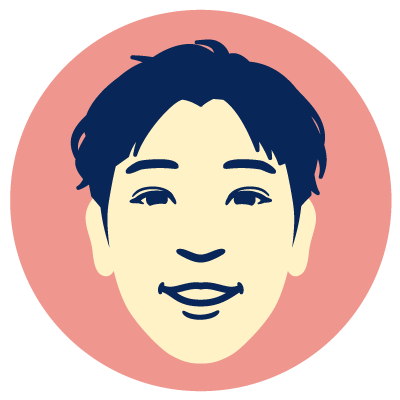
僕の妻は、たまたま出産予定日が12/28だったので、ラッキーでした。
仮に出産が予定日より遅れて、翌月になっても育休の申請は予定日で提出するので、問題はありません。
復帰するタイミングは、月末に取るのがオススメです。
というのも、社会保険料が免除されるのは、
「育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで」
ちょっと分かりづらいですね・・
僕の場合に当てはめてみます。
育児休業が終了するのは3/31、その翌日が4/1なので、前月が3月になります。
つまり、3月中までは社会保険料が免除されるということ。
例えば、3/15とか3/30までの育児休業にしていたとすると、翌日が属する月の前月が2月になってしまいます。
ということは、3月はフルで働いてないにも関わらず、3月分の社会保険料も払わないといけないので損ということですね。
なので、もし会社が許すなら、1週間とか2週間で取らずに1ヶ月単位で取った方がお得なんですね。
賞与の社会保険料も免除される
社会保険料免除のもう1つのポイントとして、賞与分の社会保険料も免除されること。
ボーナスの金額が大きい方であればあるほど、ボーナス月に育休を取得すると、かなりの税制メリットがあります。
男性の育休の場合、子どもが1歳になるまでであればいつでも取れるので、なかにはボーナス月に数日とか1週間だけ育休を取り、税制メリットをうまく利用する方もいらっしゃいます。
なので、ボーナス月が近ければ、育休の終了時期を少し後ろ倒しにしたりするのは、賢い選択だと思います。
| 期間 | 育休前と育休中の賞与比較 |
|---|---|
| 育休前 | ボーナス(賞与) ー社会保険料(健康保険+厚生年金+雇用保険) ー所得税 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー =手取り額 |
| 育休中 | ボーナス(賞与) ー社会保険料(雇用保険) ー所得税 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー =手取り額 |
おわりに
「ここで育休取ると税制メリットあるよ」というのは、会社の経理や人事の方が教えてくれるケースも多いと思います。
でも、その人が知らなかったり、教えてくれなければ、損をする可能性だってあります。
なので、自分でも知識をつけたうえで、育休を取るベストな期間やタイミングを決めるのがいいですね。
もちろんお金だけじゃなくて、自分がどれくらい育児に向き合ってみたいか、奥さんの負担を減らせるのか、ということも考えて取るといいかなと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
引き続き、男の育休、育児情報について発信していきます。
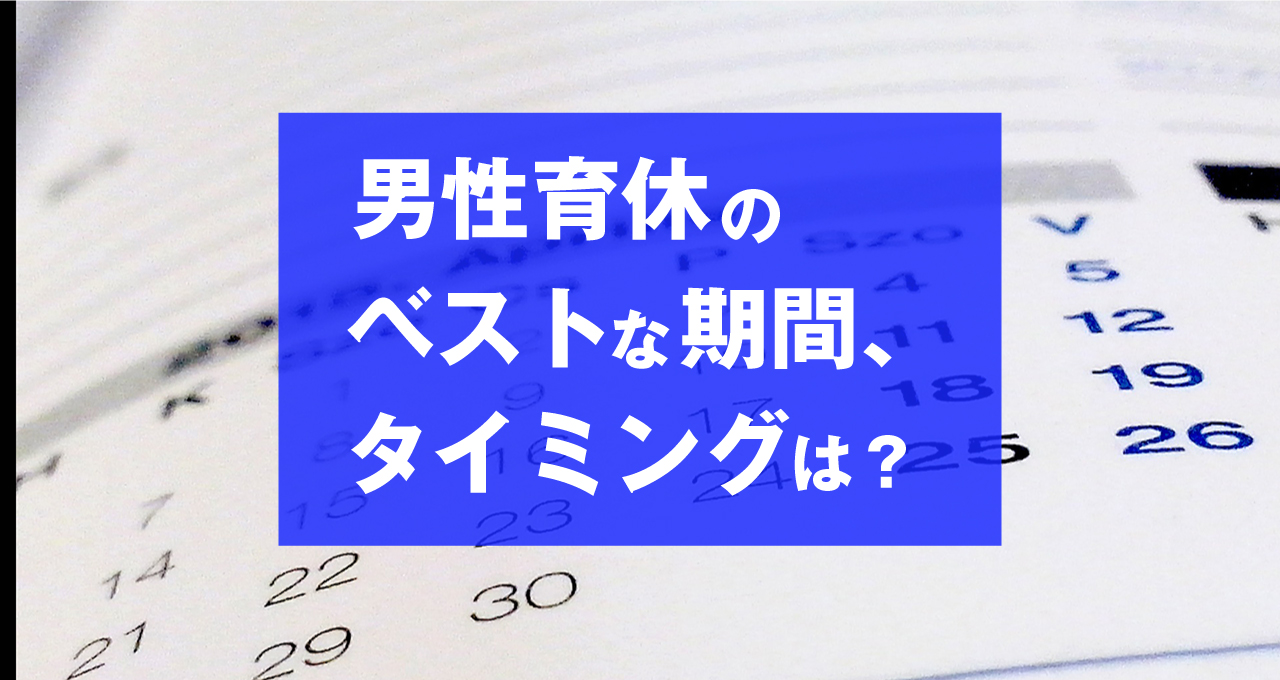
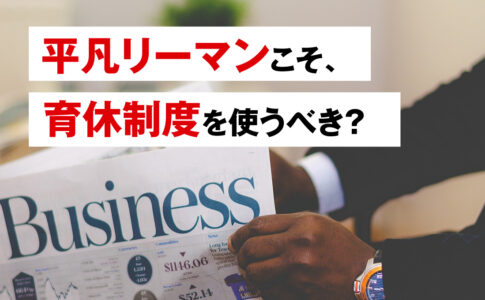
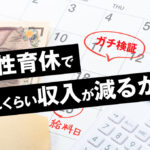




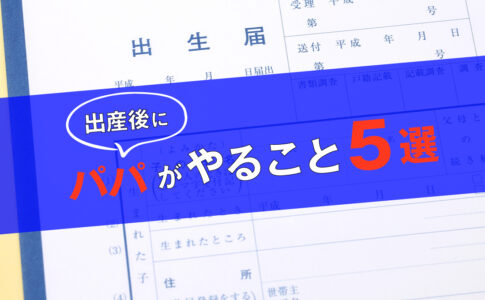
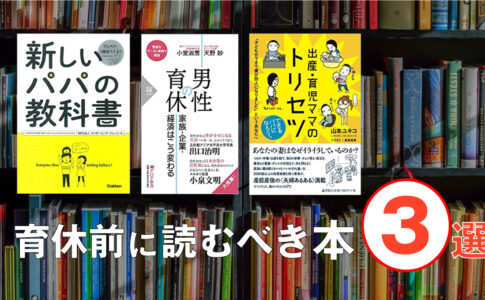
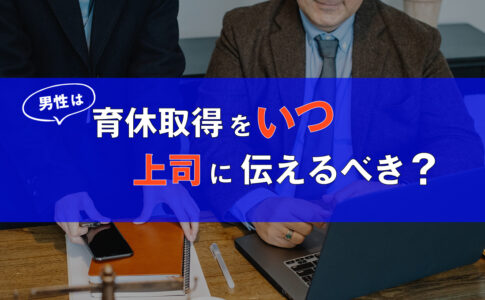
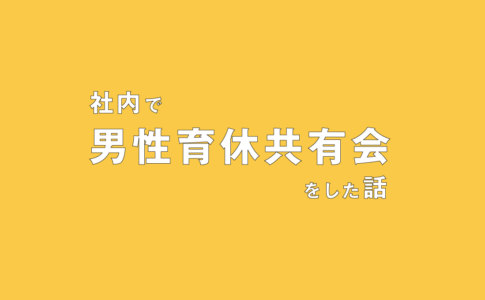
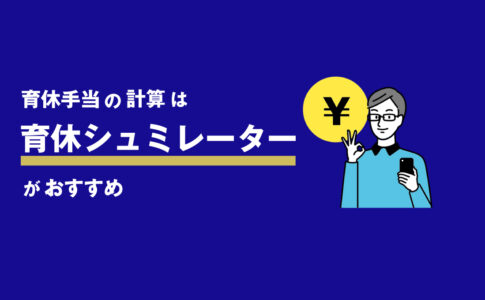


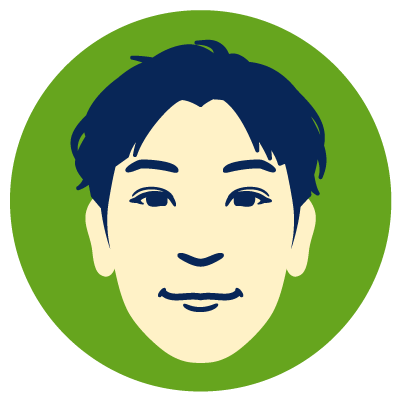
こんにちは!
2021年1月〜3月の3ヶ月間、育休を取得したKeiです。